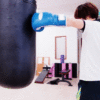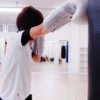この試験は年に2回あります。8月と3月です。私は、今年の3月に受けました。30点満点中24点でした。合格点は18点です。5つの分野に分かれていて、足切りが分野ごとにあります。これも難点ではありますが、しっかり勉強していれば苦にはならないでしょう。試験の難易度よりも手続きやら講習やらが非常にめんどくさいと思いました。
この試験は年に2回あります。8月と3月です。私は、今年の3月に受けました。30点満点中24点でした。合格点は18点です。5つの分野に分かれていて、足切りが分野ごとにあります。これも難点ではありますが、しっかり勉強していれば苦にはならないでしょう。試験の難易度よりも手続きやら講習やらが非常にめんどくさいと思いました。
申し込みの仕方は簡単になりますが、ネットと郵送があります。郵送の場合、申請書が必要ですが、私の場合は仕事中の合間にトラック協会に行きもらってきました。
そして、申請書類を整えても、試験を受けるまでに基礎講習を受けないと受験資格がない状態となります。1年以上の実務経験、基礎講習修了、基礎講習修了予定者という形で受験手続をすることになりますが、詳しくは、ホームページを見て参考にしてもらえればと思います。
以下参考。
実務経験1年以上
試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
基礎講習修了
国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了した方。
①貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という。)に基づき国土交通大臣から認定された講習実施機関で基礎講習を受講された方は、貨物試験の受験資格となります。
②旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に基づき国土交通大臣から認定された講習実施機関で基礎講習を受講された方は、旅客試験の受験資格となります。
基礎講習修了予定
国土交通大臣が認定する講習実施機関において、試験の種類に応じた基礎講習を受講予定の方(試験日の前日までに基礎講習を修了予定の方)。※運行管理者試験の申請と基礎講習の受講申込みは別々の手続きが必要です。 申請される方は、事前に国土交通大臣が認定する講習実施機関で基礎講習の申込みを完了してから申請してください。
※試験の種類に応じた基礎講習を修了し、試験事務センターに修了証書の写しを提出していただいた段階で受験資格を満たすこととなります。
※基礎講習が修了できなかった方、および試験の種類に応じた基礎講習の修了証書の写しが未提出の方は受験できません。
私の場合は、基礎講習修了予定者という形で、申し込んでから基礎講習(授業と最終テスト)を受けて、受験に臨む事になります。したがって落ちると今までのめんどくさいのがパーになってしまいますから一発合格を果たすことを考えた方が良いです。
上記の引用で注意したいところとして、
MEMO
基礎講習が終わった後、受講が終わると証明書が貰えますが、それを受験申請が終わった後に、追加で自分で送らなければならなかったところでしょうか。
FAXだったか、郵便だったか忘れましたが。郵便だったはずです。めんどくさかったので。てっきり講習を行った自動車学校がやってくれるものだと思っていました。
講習先によっても変わるところではあると思います。
後、合格通知が届いても3か月以内に資格者証の手続きを行わないと合格が失効してしまう制度
があり合格後も緊張感が抜けない試験だと思いました。
受験者は、色々だと思いますが一般的には運送業に従事している方が多いと思います。また、試験難易度においては、色々昨今運送業界もトラブル(事故)が続いていて高めになってきていると思います。また以下のような問題もあったようです。しっかり勉強しましょう。
平成28年度第2回試験の実施状況
1.実施状況及び合格者数について
平成29年3月5日(日)に実施した試験の合格者数等は、次のとおりです。
試験の種類 貨 物 旅 客
受験者数 29,621人 8,028人
合格者数 6,069人 2,085人
合格率(%)20.5 26.0
勉強時間は、100時間~150時間くらいでしょうか。人によると思いますので、50時間から200時間くらいでしょうか。
参考書と問題集1冊ずつで大丈夫ですが8割以上取ろうと思う方は、過去問5年分より以前のものをネットで見つけたりし解いて過去5年分にない内容を把握することも大事になってくると思います。
(実践しましたが、いまいち物覚えが悪いせいもあってか24点止まりでした。)
以下を使用。
ということで最後に成績表が、まだ最近ということもあり、ありましたので(受験申請の時に合格後、試験の成績を送ってもらうように手続き必要)載せておこうかなと思います。こんな感じです。

それでは、皆さん頑張ってください。